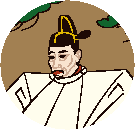 法性寺は慶長3年(1598)真如院日信上人により創建されたお寺ですが、この慶長3年8月18日「つゆとをち、つゆときえにし、わかみかな、なにわの事も、ゆめの又ゆめ」の辞世の句を残し、伏見城で豊臣秀吉が63歳の生涯を閉じています。 法性寺は慶長3年(1598)真如院日信上人により創建されたお寺ですが、この慶長3年8月18日「つゆとをち、つゆときえにし、わかみかな、なにわの事も、ゆめの又ゆめ」の辞世の句を残し、伏見城で豊臣秀吉が63歳の生涯を閉じています。この事からして、法性寺は豊臣秀吉とは少なからない縁のある寺であると思います。 中世の大坂は石山本願寺の寺内町でした。この大坂と戦をして破ったのは織田信長です。信長と本願寺のとの戦いを石山合戦といいます。信長は生前大坂に城を築いていませんが、秀吉は大坂を領してここに築城しました。天正11年(1583)5月石山本願寺旧地に着手し、30余国の人夫を使い、海陸から大名小名を集め、3年余りを費やして大坂城を完成させたのです。 秀吉亡きあとの大阪は、関が原、大坂冬の陣と続き、元和元年5月(1615)大坂夏の陣で豊臣家は徳川家康に滅ぼされてしまいます。 この冬夏2度の大きな戦いで大坂は無茶苦茶に破壊されてしまいました。その落城の後の大坂は松平下総守忠明という人の領地になります。 この松平忠明は家康の娘・亀姫が奥平氏に嫁ぎ、その間にできた子で、家康の外孫に当たる人です。 忠明は大坂に移り住むと、城の本丸・二の丸を城の地にあて、三の丸を壊して新たに新街を築きました。そして京都の伏見から町人の移住を求め、その数80余町に及んでいます。 また運河も忠明時代に開削されたものが多くあります。 寺院及び墓地の整理 大坂は豊臣秀吉によって大阪城を中心に開けてきました。そして秀吉は、この大阪城を守るため城の周囲に寺を建てさせ寺に大きな役目を持たせたようです。  忠明は秀吉が京都において、洛中の寺院を東京極に集中して都市の境目に寺町を作った故智に習い、将来における大坂の発展を予測して、大坂中の寺院を後の都市計画をする上での街の終わりと思われるところに寺を集中して建てさせました。 忠明は秀吉が京都において、洛中の寺院を東京極に集中して都市の境目に寺町を作った故智に習い、将来における大坂の発展を予測して、大坂中の寺院を後の都市計画をする上での街の終わりと思われるところに寺を集中して建てさせました。これが、東は天王寺一帯の寺町であり、北は天満の北の寺町です。すなわち市中及び接近村落の諸寺院を小橋村(おばせむら)と東西高津村及び天満村の三箇所に集めたのです。ただ一向宗の末寺については市中随所に存在することを許し、市民と同じく公私の諸役を負担させました。 法性寺も大坂市中のどこかにあったのが、冬夏2度の大きな戦いで無茶苦茶に破壊され、忠明の政策により元和の初め現在の地に移築されたものと思われます。 大阪の寺町は豊臣秀吉が作ったと思っている人が多いですが、秀吉が作ったのは京都の寺町で、大阪の寺町を作ったのは松平忠明(徳川家康の外孫)です。 薩摩屋半兵衛の事 法性寺の檀家である薩摩藩出入御用商人、薩摩屋半兵衛は幕末長崎表と商取引があり、蘭語を知る必要を感じて緒方洪庵の適塾に通学して熱心に蘭語を習いました。  この23代・24代薩摩屋半兵衛は英邁の気質を具え、義侠の風ある、商人としては稀に見る硬骨の人であったといいます。 鳥羽伏見の合戦の折には薩摩藩の軍費は一切薩摩屋の手で調えられたといい、維新当時の志士で薩摩屋の世話にならざるもの無しというほどでした。 そのような関係から新撰組に付け狙われた坂本竜馬が法性寺に身を隠したり、蘭医ボードウィンが寓居として法性寺に逗留していました。 明治27年薩摩屋の外護を受け、本堂が再建され隆盛を極めていましたが、昭和20年3月13日年の大阪大空襲で灰燼と化し、戦後の復興がなされ今日に至っています。 |
| トップへもどる |